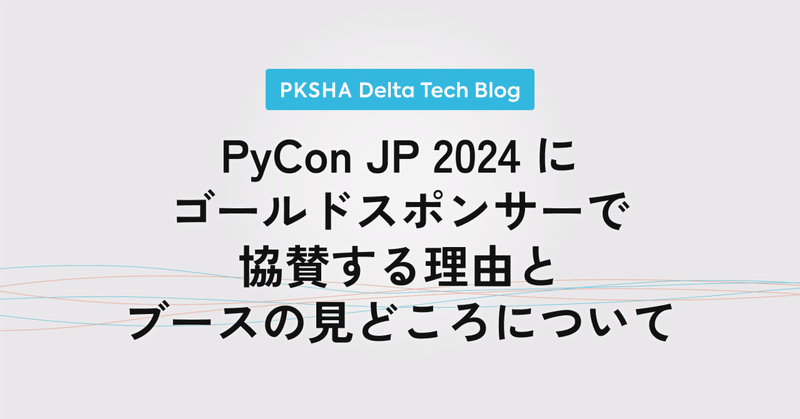PKSHA Delta
PKSHA(パークシャ)グループのnote公式ページです。
PKSHAでは、異なる才能(人と人との差分)をデルタと定義し、PKSHAのデルタを活かして社会に大きなデルタを生み出していくという意味を込めています。このnoteでは、PKSHAの様々なデルタを発信していきます。
記事一覧

Microsoft Copilot活用で業務効率アップ、AIチャットボット改善で社内の疑問を解決――未来の働き方を自ら体現するFWBBの取り組み
PKSHAグループのPKSHA Workplace(パークシャワークプレイス、以下Workplace)は「AI-Powered Future Work」をビジョンに掲げ、AIが日常業務に溶け込む未来の働き方について日々検討しています。 そして社内プロジェクトのひとつである「Future Work Black Belt(以下、FWBB)」では、未来の働き方を自らが体現することを目標に、AIツールの探索や利活用に関わる活動を推進しています。 発足から1年半、3期目を迎えた同プ

誰もが利便性高く公共交通機関を利用できる社会へ―Osaka Metroと共同開発した「AI見守りシステム」実用化に至った道のりを振り返る
2024年9月、Osaka MetroとPKSHAが共同開発した「AI見守りシステム」が56駅に導入されることが発表されました。本システムは、防犯カメラの映像に画像認識技術を用いることで白杖や車椅子をご利用のお客様の90%以上を検知することができます。 この記事では、本システムの開発及びプロジェクトの進行にあたったメンバーに、実用化までの経緯と成功要因、そして今後の展望について聞きました。 サポートを必要とする乗客を90%を超える高精度で検知――「AI見守りシステム」とは